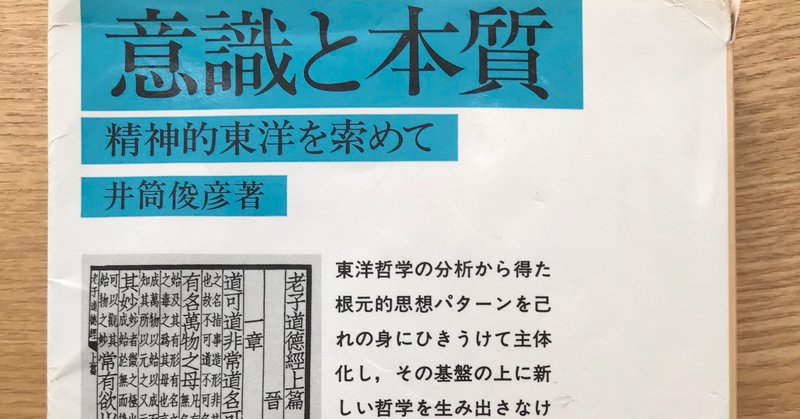
井筒俊彦『意識と本質』(5)
井筒俊彦の「意識と本質」をただ読むだけではなく、体系的に理解したいという思いで、章ごとに自分なりに概要をまとめてみる、という試み。
【基本的に『意識と本質』(岩波文庫)の本文を引用しつつ纏めています】
この章で井筒は、意識を二つの異なる方向性、垂直方向と水平方向で考えて論を進める。
まずは垂直的、縦の深まりの方向として意識に表層・深層という二層構造を想定した上で、深層意識のさらに先に、例えば禅におけるメタ意識としての「無」意識や、前章で触れた宋儒の「脱然貫通」の体験など、意識を超えた領域をもある意味「意識」という語の意味領域をぎりぎりの線まで拡張してみる。そこで見えるのは無意識や「無」意識は「意識」と密接な有機的な関係にあり、それこそ東洋哲学における意識の捉え方の最も顕著な特徴でもあるということである。
禅において「無心」という言葉が出てくる。この「無心」とは単にAに対する非Aという形での「心」の矛盾概念ではない。主体体験として、「ただ何も意識しない状態」ではなく、純粋無雑な「意識そのもの」「意識が向かう個別対象がない、意識そのもの」であると言える。「無心」は「心」のない状態であるどころか、むしろ「有心」の極限なのである。「無心」は文字どおりの無ー心ではなく、かえって「心」の基底であり、本源的に「心」そのものであるということ。つまり「意識」の究極的原点である。禅においてはしばしば「無心」と「心」が完全な同義語として用いられるのはここに由来する。つまり「無心」と「有心」が互いに全く同義的であり得るような境位がここに成立しているのだ。
一方、意識を水平方向に考えてみると、そこにはまず文化意識の問題がある。一人の人間の育った文化共同体は原初的に一つの共通言語に支えられた言語共同体であり、言語が意識を、意味論的に規制し、文化ごとに様々異なる意味体系に基づいて、様々に異なる文化的テクストが成立する。そして、それら文化的テクスト間の相違によって、人間意識も様々に異なってくる。
ここで井筒はイスラム哲学界で起きた「原子論」論争、カザーリとアヴェイロスの論争を例に挙げる。
イスラムの思想家たちはギリシャ哲学の、とくにアリストテレスの哲学の影響を受けてきた。そこから学んだ第一のことは因果律的思考、つまり世界を因果律の支配下にある一つの整然たる存在秩序として理解することである。
因果律ー火に紙が触れれば紙は燃える。Aは原因でBは結果。ある一定の条件が整えばAは必ず一定の働きを示してBという結果を生む。Aがなぜ必ず一定の作用を示すかといえば、それはある一定の性質がAに備わっているからであり、それはAの「本質」ゆえである。火には火の、火だけに固有の「本質」がある。だから火は己に触れる紙を燃やすけど、絶対に濡らしはしない。ものを濡らすのは水の「本質」に基づく水の性質だからである。
因果律の支配する世界とは、一切の事物がそれぞれ自分の「本質」を持ち、自分の「本質」によって規定され、限界づけられ、固定されている世界でなければならない。そのコスモスは前章で触れた宋儒の「理」の体系にも通じる。それは確かにひとつの美しい哲学的世界像であるには違いない。しかし因果律や、宋学では美しい「理」体系であったものが、イスラム教やキリスト教のような、セム的一神教の文化構造の中に持ち込んでくると大変な危険思想にもなりかねないのだ。
経験的世界にあるすべての存在者が複雑な因果の糸で結ばれて巨大な因果律体系をなしている。この因果の源泉はそれら存在者それぞれの「本質」である。いかなる事物も己の「本質」の規定する所にしたがってしか作用することのできない世界。もしその考えを極限までに進めたとしたらただの一つの例外もない、全く動きの取れない世界となる。つまり偶然性の否定である。もしすべてが事物の「本質」による必然によって決まるのなら、そこに神の力が介在する余地がなくなる。すなわち神の全能性に対する否定となる。これに対して異をとなえるのがイスラムの「原子論」、その大成者であるカザーリーである。
彼らは存在界を完全な偶然性の世界と見る。経験界の一切の事物を、それ以上分割できない不可視の微粒子まで分析し、それら相互の間に空間的・時間的な隣接ということ以外の何らの連結も認めない。全存在界は、互いに鋭い断絶によって分離された無数の個体の一大集積として表象される。「この世のいかなるものも、それ自体においてはなんら独自の働きを示さない」とカザーリーは言う。もし何かがそれ独自の作用力を示すとすれば、それそのものものが創造的であるということであって、神の創造能力の絶対性に抵触する。あるものAがあるものBに働きかけるということは絶対にあり得ない。火に紙を近づければ紙は燃える。だが必然的にではない。火に触れた紙が燃えないことも可能である。ではなぜ我々通常の経験上の事実として火に触れた紙が燃えるのか。それは自然界の慣習に過ぎず、その慣習は神がそうさせるからだ、とカザーリーは主張する。神から独立した因果律などあり得ない。慣習はいつでも破られる。つまり奇蹟はいつでも起こりうる。だから存在界は不確定的なものであり、人間の側からすればすべては偶然である。この偶然性の世界が事実上秩序を保持して存続しているのは、神の瞬間ごとの創造行為のおかげである、とカザーリーは説く。
それに対してアヴェイロスが反論する。因果律の否定は事物の「本質」の否定に直結し、それは一切の知識の可能性の絶対的な否定につながる無条件な不可知論だ。「理性的動物」と定義され、理性的であることをもって他の動物から区別される人間の、非人間化に他ならない、とアヴェイロスは考える。すべての存在者は必ずそれ自身の能動的作用性を持っており、各存在者の作用の源がそのものの「本質」なのである。仮に「本質」がないとすればすべての事物は名を失い、定義は無意味となり、相互に全く区別ができなくなり、全存在界はカオスとなり、理性は無力化する。そのような完全に無秩序な世界において、人はもはや何事についても何も言えず、何も知り得ないだろう。神の全能性を誤った形で尊ぶあまり、原子論者たちはこうして存在の本源的偶然性を主張するに至る。その結末は不可知論。それによって彼らは人間の尊厳を傷つけるばかりか、世界をそのようなものとして創った神を冒涜する。もし神の摂理を考えたいのなら、あらゆる事物の一つ一つにそれぞれの「本質」を与え、事物それ自体に内蔵されたロゴスから発出する作用を通じて因果律的に規定された整然たるコスモスとして世界を創った神の配慮のうちにこそ、その叡智に満ちた摂理を見るべきである、とアヴェイロスは主張する。
アヴェイロスの思想は12世紀にラテン語翻訳を通じて西欧カトリック思想界に持ち込まれ、そこで大きな波紋を起こす。パリ大学を中心に大流行しラテン・アベイロズムと呼ばれる一大思想運動が興る。危険を感じたカトリック教会は1227年アベイロズムに対し公式に異端宣告をする。彼らが危機を感じたのは、事物がそれぞれ自分自身の「本質」を持ち、この内在的ロゴスの指示するままに作用するものであり、歴史的世界の展開のプロセスに神の自由意志が介入する余地が無くなってしまうという点である。
ここで井筒は「本質」の有無という一見単純で何の問題もなさそうなことが、文化的枠組み次第で、いかに重大な思想的事態を引き起こすかということ、その具体的な一例を通じて、文化的パラダイムに色付けされた意識の在り方によって、「本質」の問題性そのものが様々に変わるということを指摘しておきたかった、と語る。

