なぜ人は美を求めるのか: 生き方としての美学入門小穴 晶子

目次(「BOOK」データベースより)
第1章 日本古代の「タマフリ(魂振り)」の思想―生命力の充溢としての美
第2章 ギリシャの哲学―価値の学としての美学の起源
第3章 中国の思想と東洋世界の美意識
第4章 キリスト教―神への思いとしての美
第5章 イスラム教―服従のアラベスクとしての美
第6章 仏教思想と日本の美意識―滅びの真理としての美
第7章 実存主義と解釈学―実存の出会いとしての芸術解釈
著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
小穴 晶子(コアナ アキコ)
1951年東京都に生まれる。1977年東京大学文学部卒業。1984年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。現在、多摩美術大学教授。(専攻/美学芸術学・音楽美学)
感想・レビュー
6
全て表示
ネタバレ
kamikawa naohide
この分野の本は難しくて途中で挫折してしまうのですが、これは読めました。どんどん読めました。いろいろな思想をわかりやすく紹介してくれてて、楽しい時間でした
ナイスコメント(0)2023/09/29
まど
扱うテーマが古代日本、ギリシャ、中国、キリスト教、イスラム教、仏教、実存主義と幅広い。やや主観的な部分もあるが簡潔に書かれていて読みやすい。それぞれの概要が理解できると思う。
ナイスコメント(0)2022/01/26
はじめ
美学はもちろん、世界宗教+儒教の宗教事情の超入門っぽくもある、かな?
ナイスコメント(0)2014/08/06
pure honor
美はそれぞれの生き方に基づいた観点だという。哲学の思想から各宗教に至るまで人は様々な思想の中で生きているのだと感じさせられた。私自身生活をしながら、どうしてこれが美徳になるのだろうかと疑問に思う考え方がいくつかあったため、それを思想の成り立ちとともに確認できて納得した。他の国ではどうか分からないが、特に日本は多くの思想の上で文化が形成されている国である。こんなに思想が混じっていたら日本人同士でも価値観が違う集団が現れていそうな気がするが、その異質性を理解することが生きる価値だと著者は述べている。
ナイスコメント(0)2014/03/29

いわちき
各思想についての概要と、その土台の延長上で語られる美について。
ナイスコメント(0)日付不明
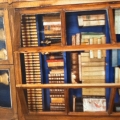
そめちん
再読したい。
===
« 小穴晶子「なぜ人は美を求めるのか─生き方としての美学入門─」(8) | トップページ | あるIR担当者の雑感(21)~トップが語る »
2011年4月 8日 (金)
小穴晶子「なぜ人は美を求めるのか─生き方としての美学入門─」(9)
このような実存の文脈で美学を考える時に欠かせないのが、解釈学なのだと著者は言います。科学が研究者の主観をゼロにして客観的に語らせようとするのに対して、歴史研究は研究者と歴史との対話と言えます。こういう事態を歴史は解釈だと表明して、その構造を明らかにしようとしたのが解釈学です。これは歴史学のみならず、美学にとっても重要な視点を提供します。例えばねクラシック音楽の演奏は作曲者の作品を解釈するという性格を含んでいるし、これを聴く鑑賞者との対話という面も無視できないからです。ポール・リクールという解釈学者は、構造主義の批判の中から解釈学を主張しました。構造主義とは、部分的な物事の意味は、それら部分の属している全体の構造によって決定されるという考え方です。このベースにはソシュールの言語学理論があります。言語の意味は社会的な習慣で決まっていて、その決まり方はまず全体があって、その全体システムが部分の価値(意味)を決定する。全体がどのように区切られ、そしてその区切られ部分が関係づけられているかよって部分の意味が決まるというものです。
この考えは、概念(意味)がそれを表わす記号としての音のまとまりに先立って存在しているという、イデア論にまでさかのぼれる観念論の否定です。概念が先に頭の中にあって、それを表わすために言語ができたのではなく、全体の構造化としての言語の成立とその意味としての概念の確定とは同時なのだというのが、構造主義の主張です。このように考えると、言語と思考は一体のものであり、言語から切り離された思考は存在しないことになります。ところで、言語の意味は社会的な慣習によって決まっているものでした。だから、思考も社会的なものということになってしまいます。もしそうなら、個人的な思考ができなくなることになる。試行は全て社会的なものになってしまうことになるわけです。
これに対して、リクールは、メタファー論を展開します。メタファーとは、簡単に定義すれば、主語と述語の関係として本来の規則では結びつけてはいけないものを結び付けて成立する表現のことを言います。たとえば、「あなたは私の太陽だ」というようなものです。これは文法的には違反の表現で訂正されるか、意味不明とされるかするものです。このとき、このような文章の読み手が、本来なら捨て去るべきものに対して、何らかの意味があるかもしれないとして保持されるのです。このときの読み手は何をしているのでしょうか。一方書き手は、社会慣習的に成立している言語を、本来の能力を超えたきわめて個人的な体験を言葉の具体的イメージをそのまま提示することで、読み手の解釈により慣習を超えた何かを伝達することを期待する試みです。この背後にあるのは、慣習に収まりきれないと感じた個人的な体験と言えますが、この個人とは、これまで考えてきた実存に重なるものと言えます。実存とは唯一かけがえのない存在としての自己であり、常に今ある自己を乗り越えて新たな自己になろうとする存在です。このような唯一の存在、他の存在と共通の尺度を持たないものとなります。共通の尺度を持たないものは、社会慣習的に定められた言語とは相容れない。さらに、実存の絶えず今ある自己を乗り越えるという性格から解釈について考えてみると、作品の意味をあれこれ考えることが解釈ですが、作品の意味として正しいもの、つまり正解が得られるものではない、ということは最初から分かっている。それでも、あれこれ考える。その理由は、作品解釈は作品の意味を確定することではなくて、解釈者自身が逆に照らし出されることが重要なことだからです。そして、最後に、解釈するということは作者の実存と読者の実存との対話となるからです。読者はこの対話によって、自己自身を知り、知ることによって、その自己を乗り越えて新たな自己となる可能性が開けてくる。そこでは、実存の絶えざる前進のための条件として、芸術作品との出会いがあるのです。
最後に、著者は思想を維持し完成するためにはイメージが必要であり、イメージは美となるために思想を必要とする。思想とイメージの相互補完関係の問題として美学を考えてきたといいます。ここでの考察の導きの糸としたのは人生観の問題です。「人生をいかに生きたらよいのか」ということです。
それで、読んでいて、これは教科書なのだなという感じが強くしました。それぞれの項目は噛み砕いてあり、分かり易くて、ここまで著者がリスクを負ってまで噛み砕いた勇気には敬服します。独善的と言われること、説明の理解に誤解を生んでしまうことも覚悟の上のことで、それでも言い切ってしまう潔さを感じました。しかし、ここで説明されていることが、羅列にしか感じられないこともじじつです。それぞれ章立てしてありますが、それが何のためなのか、なぜ、これらのものが取り上げられたのかが、肝心なことがよくわかりません。それは、実践の場でという著者のいとからすれば、一番大切なことではないのか、おもうのです。最初、お寿司の技術書と日常の料理に噛み砕いておそうざいの本で、おそうざいの視点で考えるとう姿勢ですが。それぞれの美学思想について噛み砕いてくれたものの、あくまでもすし技術をわかりやすく解説したということにとどまり、おそうざいになっていないと思いました。すし技術からおそうざいになるには、決定的な転換が必要だと思うのですが、それがなされていない。それはおそうざいの視点ですし技術を作り直すという作業です。思うに、著者はおそうざいの視点の美学とか思想というものへの変換をする前に、それがどういうものかという考察をしていないのではないかという気がしてなりません。おそうざいの視点で求められるのは何かということです。だから、人生いかに生きるべきかというという人生観で思想を見てきたといいますが、では、今、ここで生きることはどうこうことか、という著者の現実の実践が見えてこないのです。あくまでも、著者は解説者で、悪く言うと、要領よく説明していると言われてしまいそうな危険があります。そういう意味で、学者さんが書いたものという限界がよく見えると思います。著者には悪いけれど、この本を読んで、考察を始めようとは思えない。
