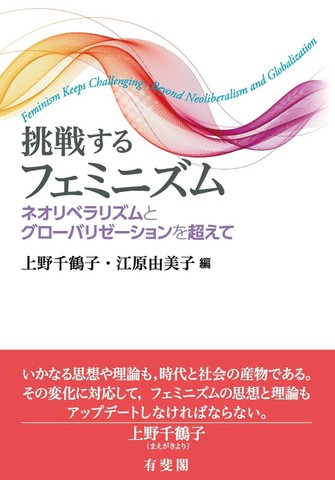
作品紹介
【「まえがき」より】
2022年,ジェンダー研究の盟友,江原由美子が新著『持続するフェミニズムのために』(有斐閣)を刊行した。そこには江原が「第一の近代」と区別して「第二の近代」と呼ぶ歴史の新しい段階に対応して,第二波フェミニズムが生み出したさまざまな思想や理論が今でも有効か,すなわち「フェミニズムは生き残れるか」という切実な問いかけがあった。
本書は,その江原の真摯な問いかけを受け止めたジェンダー研究者たちによって書かれた。世代も分野もアプローチもそれぞれに個性的なジェンダー研究者たちが,多方面から江原の設定した問いに答えようとしている。相互の論文が補い合って,フェミニズム理論の新ステージが立体的に立ち上がることを実感してもらえるだろう。
江原の新刊を読んだとたん,ここには重要な問いが書かれていると感じた上野が,共編者を引き受けた。日本における女性学・ジェンダー研究のパイオニア世代として共にこの分野を牽引し,尊敬する論争の相手でもあり,またこれまでも『日本のフェミニズム』(岩波書店)や『岩波女性学事典』(岩波書店)などの共編に関わってきたこの畏友と,再びタッグを組んで書物を世に送ることができてうれしい。
上野千鶴子
【目次】
まえがき (上野千鶴子)
序 章 今フェミニズムは何を議論するべきなのか――ネオリベラリズムとグローバリゼーションを超えて(江原由美子)
第1章 再生産費用の分配公正を求めて――家父長制と資本制・その後(上野千鶴子)
第2章 グローバル資本主義と再生産領域の金融化――「フェミニズムの相貌を気取る新自由主義」を異化するフェミニズムを(足立眞理子)
第3章 資本主義批判としてのフェミニズム――マルクス主義フェミニズムを振り返る(伊田久美子)
第4章 生産中心主義批判から,リベラリズムとの対抗へ――第二波フェミニズム理論はいかに継承されてきたか(岡野八代)
第5章 「男性稼ぎ主」型が命と暮らしを毀損している――社会政策の比較ジェンダー分析による洞察(大沢真理)
第6章 ケアの再公共化とフェミニズムの政治――福祉国家・ケア・新自由主義(山根純佳)
第7章 女性の貧困の再考察――長期時系列データから(阿部彩)
第8章 女性労働のゆくえ――能力発揮をフェミニズムはどのようにとらえるか(金井郁)
第9章 フェミニズムと戦争・軍隊――21世紀の新たな難問(佐藤文香・児玉谷レミ)
第10章 フェミニズムの新自由主義化に抗う――女性解放の現代的課題(三浦まり)
あとがき (江原由美子)
【編者紹介】
フェミニズムのパイオニアであり今なお圧倒的存在感でリードする2人が編者としてタッグを組み,フェミニスト社会科学の第一線で活躍する研究者を束ねて実現した本です。ネオリベラリズムとグローバリゼーションという大きな社会変動下で,資本主義自体が変質した今,フェミニズムは何を議論すべきか,徹底的に追究します。
*上野千鶴子(うえの ちづこ)
東京大学名誉教授
主著 『家父長制と資本制――マルクス主義フェミニズムの地平』岩波書店,1990年(岩波現代文庫,2009年)。『ケアの社会学――当事者主権の福祉社会へ』太田出版,2011年。
*江原由美子(えはら ゆみこ)
東京都立大学名誉教授
主著 『ジェンダー秩序』勁草書房,2001年(新装版,2021年)。『持続するフェミニズムのために――グローバリゼーションと「第二の近代」を生き抜く理論へ』有斐閣,2022年。
===
書 評 DOI:10.24567/0002005345
青山 薫 *
* 神戸大学国際文化学研究科教授
ジェンダー研究 第28号 2025年
85
新自由主義とグローバル化による困難な時代に
「フェミニズムは生き残れるか」という、江原由美
子の問い(江原2022)から本書は始まる。
そして、
フェミニストや女性だけでなく、人類が、生き残
るために必要なフェミニズムの展開をめざす。江
原の問いは、ナンシー・フレイザーの「フェミニ
ズムは資本主義の侍女となってしまった」―グ
ローバル化に伴う格差の拡大も、女性の貧困化さ
えも見逃し、一部のエリート女性だけが資源や
選択肢や能力を獲得する新自由主義に加担した
(Fraiser 2013=2019)という批判に対する反問でも
あり、本書は、これをわがこととして受け止めた
上野ほか各論者からの応答である。
上野千鶴子(第1章)は、『家父長制と資本制』
(岩波書店、1990年)刊行後30年間の変化を論じ、
グローバル金融資本主義の中で、プロレタリアー
トは「階級的主体になりえない」(35-38頁)プレ
カリアートとなり、南北格差は移民と使用者の差
として国内にも存在するようになり、ジェンダー
間格差も、女性間・男性間格差も拡大したことを
指摘する。
これを受けて足立眞理子(第2章)は、金融危機
以降の「フェミニズムの相貌をもつ新自由主義」
(70頁)と「再生産領域の金融化」(92-94頁)の関
連をひもとく。家計・世帯に金融取引のメカニズ
ムが浸透し、学費も年金も、ひいては再生産その
ものも、労働力のコストではなく「投資」となる。
同時に、男性の「短期で無茶な決定を諫め」(96
頁)、投資のリスクを抑えることができる新たな
女性像が創られる。
そこで伊田久美子(第3章)が、資本主義批判
としてのフェミニズムを再評価する。第二波フェ
ミニズムは、「妻」「母」でない一人称の女性主体
を登場させ、性と生殖と女性の身体の解放を主張
し、「私的領域」を劣位に置く近代国民国家に異
議を申し立てた(113頁)。3点を結ぶ「個人」は多
様で、先進国中心主義に異を唱え、第三波に続く
フェミニズムのネットワークと連帯を開いた。
岡野八代(第4章)にとっては、リベラリズムの
価値を手放さず、ポスト構造主義におけるアイデ
ンティティの構築も有効とするのがフェミニズム
である。それは、「個人の選択」を促すリベラルな
資本主義の複雑な抑圧構造を理解可能にする。例
えば、母親「業」を疎外・搾取といった労働概念に
関係づけ、「ケアの倫理」(148頁)へとつなげる。
フェミニズムは、「個人の選択フェティシズム」
(152-153頁ほか)を脱し、分かち合いの倫理を築
いたのである。
しかし日本では、強固な「男性稼ぎ主型」生活
保障が機能不全を起こしている。それを大沢真理
(第5章)が明らかにする。ひとり親家庭の貧困率
が非常に高いことより衝撃的なのは、0~4歳と
25~29歳の女性で、国による所得の再配分を経
て余計に貧しくなる点である。大沢はこれを、女
性が働くこと、産み育てることに制度が「罰を科
している」(178頁)と言う。「罰」は、家父長制社
会におけるミソジニーの具現化である(184頁)。
山根純佳(第6章)は、ケアをめぐる新自由主
義的改革とフェミニズムの関係に焦点を当てる。
フェミニズムがめざすケアの「脱家族化」は、現
在、低賃金と「再生産労働の国際分業」によって成
り立っている。ケア市場の拡大と公共機関の民営
化が労働者の待遇を悪化させ、ギグワーカーと移
民を増加させている。無償ケアのために賃労働を
制限される女性と、ケアサービスを外注できる女
性の格差を広げている。フェミニズムは当事者運
動と連帯し、ディーセントな家事・ケア労働を計
画するべきだ、と山根は主張する(210-211頁)。
女性と子どもの貧困をデータで裏付けてきた阿
部彩(第7章)は、配偶者「死別」女性と「未婚」
上野千鶴子、江原由美子編(有斐閣、2024年)
挑戦するフェミニズム ネオリベラリズムとグローバリゼーションを超えて
女性の貧困リスクに注目する。この30年余で「死
別」女性の貧困リスクは高齢者で上昇し、かつて
「看取り保証」(220頁ほか)とも呼ばれた「死別」
への所得保証は弱まった。未婚女性の貧困率は就
労世代で上がり、高齢者で下がったがいまだに4
割ある。均等法に代表される労働市場改革は、ケ
ア負担の少なさから男性同等に働けるはずだった
未婚女性の利益にさえならなかったのである。
以上から、3号被保険者制度や遺族年金を批判
して縮小・撤廃するのではなく、女性に対する防
貧機能を認め、取り戻そうという阿部の結論(237
頁)は発想の大転換と言える。
労働市場における格差と女性の関係について
は、金井郁(第8章)が検討する。1990年代以降、
補助役だった女性労働者が能力発揮の主体とみな
されるようになってきた。ここで、エリート女性
だけのネオリベラリズムに抗するため、金井は
アマルティア・センのケイパビリティ概念(Sen
1992=2018)を導入する。何かを実現するために、
「個人の選択」ではなく、抑圧構造・権力関係を問
題にするケイパビリティは、構造的変化のために
集団的エイジェンシーを要請する。これによって
女性は連帯し、格差を変革し得るのである。
佐藤文香と児玉谷レミ(第9章)は、女性兵士問
題の新展開を見る。グローバル化と新自由主義の
中の「新しい戦争」(264頁ほか)では、人道支援
など戦闘以外の任務が増し、女性兵士の包摂が進
行した。そこに、フェミニズムの知が取り込まれ
ている。国家はさらに民間の軍事安全保障会社を
使い、市場を通じて、軍隊のジェンダー化、人種
化、階級化された権力構造を損なわない暴力も行
使する。「新しい戦争」は交差的な格差を縮小させ
ず、私たちはさらに批判的な知を模索するほかな
い(279-280頁)、と佐藤・児玉谷は結ぶ。
最終章では三浦まり(第10章)が、フェミニズ
ムと新自由主義化の力学を改めて読み解く。ま
ず、男女賃金格差が大きく女性管理職割合が低い
日本で、新自由主義に加担した、とフェミニズム
の罪を問うのは現実的でない。新自由主義による
ジェンダー平等の道具的利用が、あたかも反女
性差別に見え、左派的な反新自由主義と右派的
な「反・反差別」が共振することもある(298-299
頁)。「個人の選択」によるトランスジェンダーの
権利と女性の安全が対立させられ、反新自由主義
と「女性を守る」名目のミソジニーに女性たちが
取り込まれる例も、三浦は挙げている(300頁)。
このように、確かに困難な状況に向き合い真に
迫る各章の、連帯の結節点はどこにあるのか。乱
暴にまとめれば、新自由主義と対立するケア中心
の社会を構想し、「男並み」の女性登用に引き込ま
れないこと、「母親罰」の撤廃とケアの権利をめざ
すこと、個人が生き延びるだけでなく、差別・抑
圧の構造を変革するような集団的エイジェンシー
をはぐくむこと、である。まさに人類が生き延び
るために必要不可欠な結節点と思われる。
一方、本書に対する小さな不満を挙げるとすれ
ば2点。やはり第二派フェミニズムが公のものに
したセクシュアリティの政治性についてと、フェ
ミニズムをも揺るがすジェンダー二分法そのもの
に対する疑義について、ほとんど触れられていな
いことである。どちらも新自由主義とグローバル
化に深く関わる。とはいえ、これらもふまえた挑
戦と連帯を求めつつ、フェミニズムが今後も生き
延び、必要とされる道を本書は照らしている。
江原由美子,2022,『持続するフェミニズムのために
―グローバリゼーションと「第二の近代」を生
き抜く理論へ』有斐閣.
Fraser, Nancy. 2013. “How Feminism Became
Capitalismʼs Handmaiden - and How to Reclaim
It: A Movement at Started out as a Critique of
Capitalist Exploitation Ended up Contributing Key
Ideas to Its Latest Neoliberal Phase.” The Guardian
website, Oct. 14, 2013.(菊地夏野訳, 2019,「フェ
ミニズムはどうして資本主義の侍女となってし
まったのか―そしてどのように再生できる
か」『早稲田文学』2019年冬号,筑摩書房.)
Sen, Amartya. 1992. Inequality Reexamined. Russell Sage
Foundation.(池本幸生・野上裕生・佐藤仁訳,
2018,『不平等の再検討―潜在能力と自由』岩
波書店.)
