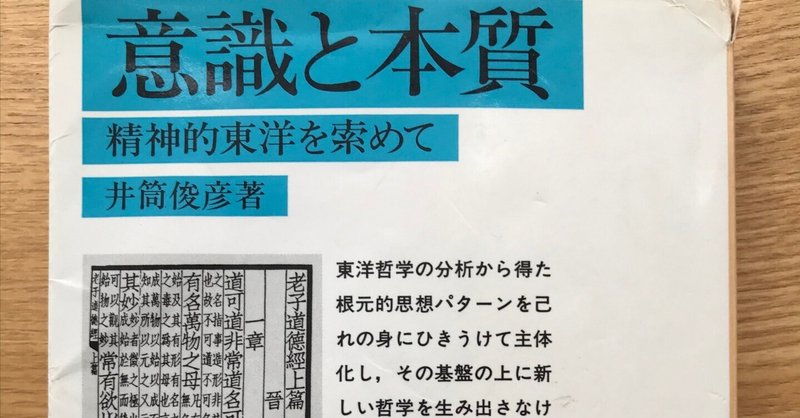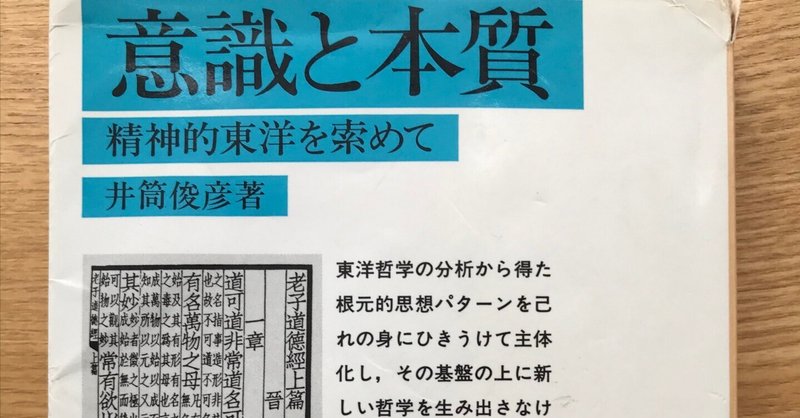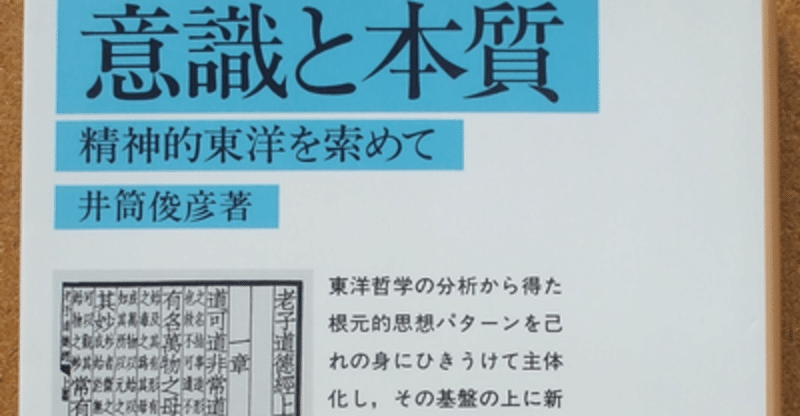
意識と本質への道
井筒俊彦「意識と本質」は、自分にとって青春の書である。また、生涯かけて挑み続け、読み続ける本なのだと思っている。
出会いは浪人時代だった。東大の過去問という形で、唐突にそのテキストは目の前に飛び込んできた。意識とは外部の対象に向かっていくものであり、その外部の対象をそれと意識するためには、あらかじめその本質が把握されていなければならない、ということを語っていた。
さっぱり意味がわからない。けれど、どこか面白い。よくわからない興味を掴まれて、ずっと印象に残っていた。後日、古本屋でふと手にとったのが岩波の原著で、その文章は序文にあたるものだったのだと知った。
その序文がこれまた衝撃的だった。著者の狙いは、老子や般若経典といったインド中国のおなじみの古典世界だけでなく、禅や日本的哲学はもちろんのこと、イスラム世界の哲学も含め、東洋全体の哲学体系と近代西洋哲学のすべてをスコープに入れて、全人類の哲学の総括し、「共時的構造化」をしようと試みているのだという。なんたる野心。そんなこと、普通考えるだろうか?ひとつなぎの大秘宝を手に入れようとする少年海賊の心意気さながらである。
当然ながら、参照すべき文献や資料は極めて多岐にわたり膨大であることから、この本は自分がやりたい仕事の序文のようなものになるだろう、とのことだった。しかるに、いま書いているこの序文は、自分がやりたい仕事の全体像からしたら、「序文の序文」にあたるのだと、こういうことであった。
自分が一番最初にショックを受けた文章は、その「序文の序文」の最序盤にあたる導入部分であったのだ。それすらもが難解であったわけだし、現に東大の入試問題として取り上げられるぐらいの文章なのだ。この人の知的営為の「序文の序文の導入」ですらも、自分にとっては取り付く島もない岸壁のようなものだったわけで、そういう文章が存在するということ自体に、ただひたすらに畏敬の念を抱いた。
その本は、最初に古本屋で手に入れて以来、何度も引っ越しをしたのだが、決して手放すことはなくて、5年に1回ぐらい、読み返してきた。そして昨夜また性懲りもなく「序文の序文の導入」を読み返してみて、最近得た色々な気づきのおかげか、以前よりも読めている自分に気づいたのだった。
問題意識は、「実存」→「本質」→「名」→「意識」という流れにある。本来、実際に存在している物理的世界には名前などついていない。勝手に人間が、あれは山、これは花と名前をつけたに過ぎない。富士山だろうが高尾山であろうが、「山」と意識できるからには、「山」と定義されるための本質があるはずだ。しかし、古典的な仏教哲学の世界では、そのような本質は、「虚妄」であるとして、徹底的にその虚構性を論じる。
確かにそれは一理ある。
例えば、人間が、何かを「恥」だと感じる。しかし、一体、何が「恥」なのか。それを支える客観的実存は存在しない。あくまで、心のなかに揺らめくなにかでしかないし、その名を与えなければ、知覚すらされないかもしれない。
感覚や感情のような形のないものだけではない。具体的な物、例えば、富士山でもいい。富士山とは、どこからどこまでが富士山なのか。山頂から中腹、裾野へと降って行った先には関東平野まで当然地続きであり、つながっているからには平野もまた富士山の一部であり、富士山もまた平野の一部であるという不思議なことが起きてしまう。生物学における「種」にも似たような話があり、交配可能なものどうしを同一の種だと定義するのが一般的なのだが、博物学的な分類とこれは一致しない。
こういう話をすると、近代的な感性を持つ人間は相当動揺する。足元がぐらぐらする感じを覚える。所与のものだと思っていた認識世界が、実はフィクションだったのかもしれない。しかし案ずることはない。禅者とは、世界を意識的認識論のなかで眺めているわけではなく、言語化され客観的な死物として概念化される前の段階、無意識的認識によって世界を見る。そういう訓練を積むことで、世界の崩壊は免れると、まあ、そういう話が導入部分で展開される。
久しぶりに読んで思ったのが、「定義」や「本質」がやけに万能である前提すぎやしないかということだった。人間の認識の基礎は本当に「本質」にあるのだろうか。人間の認識の基礎が、「本質」にあると考えるから、混乱しているのではないか。龍樹の言うところの、これは山ではない、山でないこともない、山か山でないかということでもない、というような、否定に否定を重ねて「空」を背理法的に証明するようなアプローチになってしまう。悪いのはきっと「本質」への信頼なのだ。
「プロトタイプとの距離」という最近の認知科学における「非・定義的」な認知システムを前提として論理体系を組み立てることで、まったく違う哲学世界が拓けるのではないか。「定義」や「本質」の万能性を疑うという発想が、この、わかったようなわからないような不思議な理屈に風穴をあけることに繋がるのではないか。