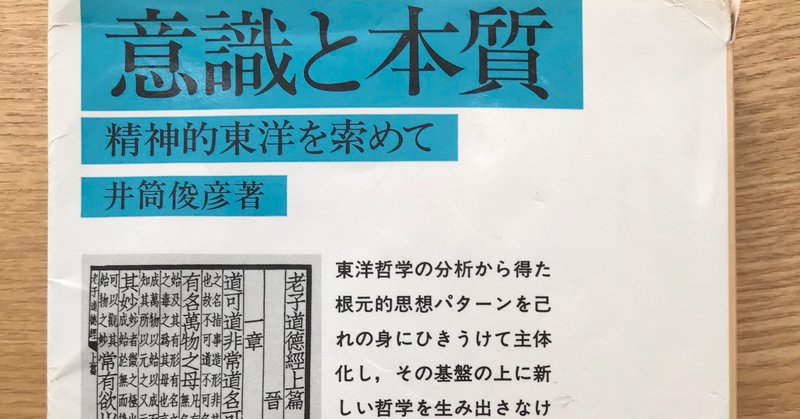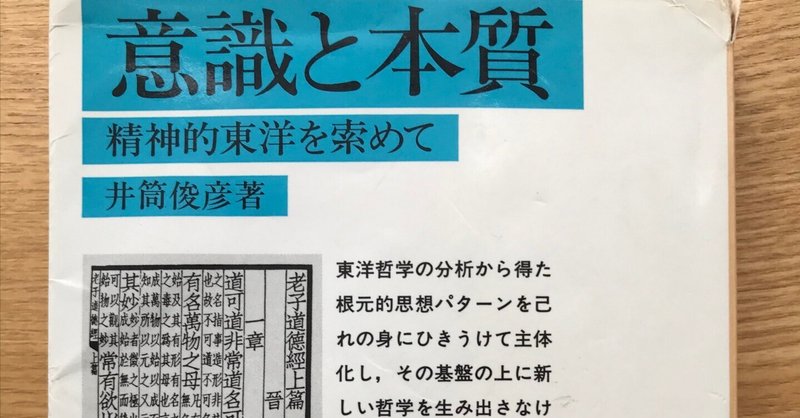
井筒俊彦『意識と本質』(8)
井筒俊彦の「意識と本質」をただ読むだけではなく、体系的に理解したいという思いで、章ごとに自分なりに概要をまとめてみる、という試み。
【基本的に『意識と本質』(岩波文庫)の本文を引用しつつ纏めています】
前章では無分節的に、直接無媒介的に事物と対峙し、事物を無「本質」的に見るあり方を、禅を例に触れた。
しかし、この本の本筋は、普遍的「本質」・マーヒーヤを単なる抽象概念ではなく、濃密な存在感を持ったリアリティとして実在するものとしてとらえ、その実在をどの意識の層でとらえるか3つの類型について語るところである。1つ目については四章のマラルメ、宋儒を例に述べた。この章では2つ目の類型…「元型(アーキタイプ)」的本質論、すなわちある種の人間の意識深層に生起する「元型(アーキタイプ)」イマージュの形象性のうちに、事物の「本質」の象徴的顕現を見ようとする立場について語られる。
人間の意識はつねにイマージュを介在して事物を見ている。それは深層意識だけではなく表層意識でも同様だ。目の前に一本の木が立っていたとして、我々がそれを木として認識し、そこに木「の意識」が成立する。実在する木を見ている限り、木「の意識」の成立に参与するイマージュの働きは気づかれない。木から目を背けて、(思い返したり、残像だったりで)我々の意識に木が現れる時、初めて我々はそこに働く木のイマージュに気づく。我々があらゆるものを見るときには、このイマージュを介在して見ている。表層意識、日常的意識においては事物とイマージュが一体になっているのでそのことに気づくこともない。
しかし何らかの刺激で意識が興奮し、あるいは弛緩した時に、イマージュが現実的事物との結合が解かれ、遊離し、日常的意識の世界では見たことのないような異様な光景としてたち現れることがある。日常的意識、表層意識の立場からはそれを妄想とか幻想としてとらえられるが、深層意識からみればそれらは妄想や幻想ではなく、真の意味での現実であり、存在深層の自己顕現なのである。この種のイマージュに重要な役割を見出してきた東洋思想の代表にシャマニズムや、密教などがある。
イマージュ体験における表層意識から深層意識への推移を最も原初的に現しているものがシャマニズムである。ここでは古代中国のシャマニズム文学の最高峰をなす『楚辞』を例に考察する。
『楚辞』に現われるシャマン的実存は自我意識の3つの層、3つの段階からなる意識構造体として考えられる。第一は経験的自我を中心とする日常的意識。第二は「自己神化」の過程において次第に開かれていく脱現実的主体性の意識。第三は純然たるシャマン的イマージュに遊ぶ主体性の意識。
第一の層ではシャマンは一個の常人にすぎない。『楚辞』の主人公たち、特に屈原は並外れた人物。純粋潔白な彼は、不義不正が渦巻く俗社会から疎外され、自らを悲劇的実在として捉える。世俗に対して一点の妥協も許さない廉潔の士。しかしこの意識次元で彼が提起するのは道徳のそれであり、シャマン的主体ではない。
第二の層ではそれに反して、彼の意識は日常的人間の主体性からシャマン的主体性に変貌する。「聖なるもの」に近づくことによって聖化されていく意識の主体的変貌がそこに看て取れる。
人間的主体は人間的世界に住む。だから社会的、自然的現実の具象的事物も彼の視界に入ってくる。彼の見るものは神々や妖鬼や飛竜のような超現実的存在者だけではない。聳える山、流れる水、咲く花…日常生活において、意識の第一段階の働きを通じて慣れ親しんだあらゆるものが、第二段階に移った彼の意識の目にも映る。だがこの状態でのシャマンは、日常的人間主体ではなく、半ば「神化」された意識状態にあり、彼の意識に映る山や水や木は名状しがたい幽邃な様相を帯びる。彼の目は神を眺める人間の目であって、神の目ではない。だがそれでも彼の意識はシャマン的脱自状態にある。『九歌』の「湘婦人」では、湘水の女神が恋い焦がれるシャマンの設けた祭壇には降下せず、湖水を隔てた北の渚に降りる。遠い彼方に光る女神の姿。「神人合一」の期待は外れて、シャマンは人間的実存の次元に残り、彼の心は暗い悲しみに翳る。「嫋嫋と秋風吹き渡る洞庭湖は一面に波立って、岸辺の木の葉が風に散る」そんな彼の意識に映った自然は普通ではなく、半ば「神化」されたシャマン詩人の意識に映った心象風景なのだ。トランス状態にあるシャマンの意識には山や水などの普通の事物も、経験的事物とは無縁な神々や天人や妖鬼と全く同資格で登場し、全体が茫洋とした幻想風景として現われる。
そして第三の層においては、第二の層のように経験的事物から想像的イマージュに変貌するプロセスは必要とされない。ここでは山があっても百神の住む崑崙山、樹木も高さが数千丈にも及ぶ世界樹のように、最初からシャマンの意識そのものが純然たるイマージュ空間なのである。経験的世界の事物の重みを感じさせるものは一切ない。身の丈千丈の巨人、全てを溶かし尽くす十個の太陽、千里の流砂、象のような赤蟻、三つ目で頭は虎、体は牛の国王が血の滴る手でつかみかかってくる…無防備な魂には多くの危険が潜む。しかし本物のシャマンは人間の魂にかけては偉大な専門家、魂の旅するイマージュの国の地理を隅から隅まで知っている。一時的に肉体を脱したシャマンの意識主体は、天空を馳せ巡って、この世ならぬ「遠遊」を心ゆくまで楽しむのである。
こうしたシャマンの意識次元に現われるイマージュは、本質的に「神話創造的」である。しかしそこからさらに哲学的思惟を深め、そのイマージュ空間を雄大な哲学的世界観にまで展開させたのが、莊子であり、空海の密教的仏教であり、ユダヤ教神秘主義・カッバーラーであり、イスラム思想におけるスフラワルディー系の照明哲学などである。莊子の冒頭で描かれる、背の広さ幾千里を超えた鵬などは哲学的象徴性に満ち、空海の金胎両部マンダラは「想像的」イマージュ空間の構造的呈示である。
イスラム神秘主義のスフラワルディーはこうしたイマージュ空間を「形象的相似の世界」と呼び、想像的イマージュをアシューバーハ・ムジャッラダ…「物質性、経験的事実性を離脱した、似姿」と呼ぶ。経験界の事物に似ているけど、物質性を欠くのでフィジカルな手応えがある事物ではなく、それらとは似て非なる存在者、を意味する。
これと同じ観点からスフラワルディーは「似姿(アシューバーハ)」を「宙に浮く比喩」とも呼ぶ。存在次元の「移し」によって、物質的、質料的な経験界の存在次元から、非質料的存在次元に「運び移され」て、そこで異次元的に、「宙に浮いて」いる存在者である。日常的意識で見る人にとっては質料性を欠く「比喩」は物質的事物の「似姿」であり影のような存在なのかもしれないが、スフラワルディーにとっては、我々のいわゆる現実世界の事物こそ影のような存在に過ぎず、「比喩」や「似姿」のほうこそ存在性の真の重みがあるのだ。「似姿」や「比喩」はこれまで述べてきた「イマージュ」であるが、単に心に浮かぶ事物の映像ではなくて、脱質料的な存在次元に現成するれっきとした実在なのである。例えばスフラワルディーが「光の天使たち」について語る時、彼にとって天使は単なる心象ではなく、存在の異次元、彼の言う「黎明の光の国」に実在するのである。
想像的「イマージュ」は深層意識的イマージュであり、深層意識領域において「元型(アーキタイプ)」の形象化として、事物の「元型」的「本質」を深層意識的に露顕させるのだ。